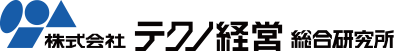現状維持バイアスとは何か
人間の脳は、毎日膨大な量の情報を判断している。その都度、一から全てを把握して判断し、決定を下していてはとてもではないが脳の処理に使用するエネルギーが足りなくなる。そこで、脳は省エネ機能を発動させる。過去の経験や先入観をもって判断のスピードを上げ、必要なエネルギーを最小限に留めるのだ。こうした心理傾向は「認知バイアス」と呼ばれており、人間が進化を辿ってきた過程の中で獲得したある種の本能とも呼べるもので、抗うことが難しい要因の一つとなっている。
現状維持バイアスもこの認知バイアスの一種とされており、新たな選択肢に伴う不確実性を避けるために働く心理傾向だ。つまり人は、本能的に未知のリスクを避け、現状を優先するようにできている。その方が危険を避けることができるためだ。見たことも触ったこともない、得体のしれないものは、いくら空腹であっても口にしない、といった感じだろうか。現代で置き換えるのであれば、例えば、毎朝食べている食パンが無くなった際、たいていは同じ商品を購入するはずだ。そう簡単に違うメーカーや商品に変えたりしないのではないだろうか。製造業においては、特にこの傾向が顕著に現れる。長年の習慣や実績が、どうしても新たな変化への抵抗を強めてしまうのだ。
製造業における現状維持バイアスの影響
変化や未知のリスクを避け、そのままであることを優先する現状維持バイアスは、工場の生産性や競争力を低下させる大きな要因となる。例えば、老朽化した設備を使い続ける決断がその典型だ。「まだ使える」という理由で、新たな投資を先送りにする企業は多い。その結果、他社が最新の生産技術を導入して効率を高める中、自社だけが取り残されることになってしまう。また、工程の改善やデジタル化が必要と分かっていても、現場の慣習を優先し、具体的な行動を起こさないケースも少なくない。「これまでのやり方で問題ない」という思い込みが、新たな成長や長期的な視点での変化を妨げている。
現状維持バイアスを乗りこえた成功例
ある製造会社は、従来の生産ラインを全面的に見直す決断を下した。新しい設備の導入やAIを活用した生産管理を取り入れることによって、作業効率が30%向上。従業員との対話を重ね、変化に対する不安を解消することによって、バイアス=本能の克服へとつながったのだ。別の事例では、経営者が自ら現場を視察し、課題を肌で感じたことが転機となった。現状維持バイアスを認識した経営者が変化を決断して強いリーダーシップを発揮し、従来の固定観念を捨てた結果、業績は回復基調に転じた。
現状維持バイアスを克服するアクションプラン
現状維持バイアスを克服するには、まずその存在を認識することが重要だ。自身の意思決定を振り返り、変化を拒む理由が合理的かどうかを検証する必要がある。自社のことを客観視することが難しい場合は、第三者や外部のアドバイザーに意見を求めるのも効果的だろう。次に、現場の声を積極的に聞くことが求められる。現場の慣習や抵抗を理解し、変化を起こすことによって実現する具体的なメリットを示すことで、従業員の納得を得ることができる。最後に、小さな変化から始めることが有効だ。一度に大きな改革を求めるのではなく、部分的な改善を繰り返すことで、変化への心理的なハードルを下げることが可能となる。
変化を恐れず未来を描く
現状維持はリスクである。環境が変化する中で、現状を維持することは停滞を意味する。経営者は、勇気を持って新たな一歩を踏み出さなければならない。現状維持バイアスを乗りこえた先にこそ、新たな可能性が広がっているからだ。製造業の未来は、変化を受け入れる意思決定にかかっているのではないだろうか。