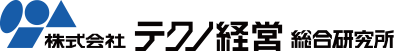「品質経営」とは、企業が顧客に製品やサービスの品質だけでなく、顧客価値創造も含めて総合的なCS(顧客満足度)の強化をめざす考え方です。自社の製品やサービスがその品質の高さ故に顧客に選ばれてきた、という自負のある企業の経営者においては競争優位の源泉として大切にすべきものであり、経営理念に明記されていることが多くみられます。
実際にそのような企業のモノづくりの現場では品質に対する意識も非常に高く、自社の製品やサービスへのプライドを感じます。しかし、中には品質に対する意識が行き過ぎて、他のこと、特に生産性に対しては鈍感になり、利益の機会損失をしているのではないかと思われる現場もあります。もちろん、品質を高めることは顧客の価値を高めることにつながり、対価を払ってくれれば利益も増えるのでしょうが、多くの場合は顧客が求める一定水準の品質をクリアできれば、それ以上の対価をいただけることはありません。
それならば、現状の高い品質水準を維持しながら生産性を追求し、利益を増やしていきたいところですが、多くの経営者が心配する点は「生産性を追求し始めると高い品質水準を維持できないのではないか」ということです。
しかし、正しいやりかたをすれば、そのような心配は必要ありません。むしろ、正しく生産性を追求していく過程で現状の品質水準は強固に安定したものとなります。
正しい生産性を追求するポイントは2つ。1つは守るべき品質水準を明確にすること、もう1つは品質に影響するプロセスを明確にし、そのプロセスには原則として変更を加えないことです。あたりまえのことのように思われるかもしれませんが、品質の基準やプロセス、つまり作業方法を現場にまかせている部分が多い企業ほど実行が難しく、生産性の追求が進まない、あるいは品質レベルが維持できなくなります。品質と生産性がトレードオフの関係になるいわゆる「品質と生産性の天秤」が生まれるのです。
真の「品質経営」というのは顧客が求める品質レベルを正しく把握し、同時に利益を追求しながら企業自身も成長することによって、更なる顧客価値の提供を拡大していくことではないでしょうか。
また、真の「品質経営」は現場の管理者や作業者の意識も変えることになり、更なる成長を促します。